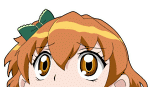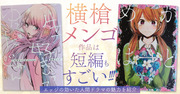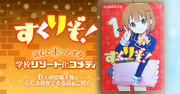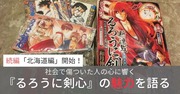倉橋数子は、バリバリの学業エレベーターのトップでありながら、おそらくその本質は極めて「大衆」的なのだ。
彼女の不幸はその本質的な大衆性でありのままに勝負できるほど、時代(『雑居時代』は1982年刊行)が追いついていなかった点にあるのである。
ここで言う「大衆」とは、現代に蘇るべき知の一つであるスペインの鬼才オルテガの著作『大衆の反逆』(1930)で定義されているような意味での「大衆」であるが、その概念は時代を先導する少数の「少数者」と、大多数の「大衆」との対照で捉えられる。
一昔前、少数者の特権であった安全・生活様式・娯楽、そして自由を大衆が十二分に謳歌している現代は、「大衆」の時代であるとオルテガは言うのだ。近年ではさらに大衆が手にした特筆すべき能力として、「メッセージや表現を大多数に発信する力」があげられるだろう(根本は技術の革新に求められ、それはいうまでもなくインターネットの発達と普及である)。
1982年、颯爽と現れた少女小説史に残るヒロイン、倉橋数子は、学業エレベータを上り詰めて一握りの「少数者」に入ることを自身に課しながら、抗いようのない自身の「大衆」性に引き裂かれて、何事も上手くいかない女の子である。幸せか不幸かで言ったら、ぶっちゃけ彼女は見ていて不幸な部類に入る。何しろエンディングが、あこがれの叔父さんのために学業エレベータを凄まじい努力で上っていたのに、叔父さんは彼女の気持ちなど知らずに自身の学業を追究して彼女を置いてドイツに行っちゃうという、恋が成就してどうこうというそれまでの少女小説とは決定的に違い過ぎるエンディングなので。
数子、家弓、勉の3人の雑居生活を描いた『雑居時代』には、「大衆」側のヒロインとして家弓が登場する。あろうことか彼女は漫画家志望で、学業エレベータのトップである数子とは、存在そのものが違い過ぎる。読んでる本からして、数子は岩波新書のプラトンで、家弓は少女漫画である。なのだけど、最終的に数子はぐっと家弓よりの大衆性に巻き込まれていく。彼女らが雑居生活する花取邸を止む得ぬ事情でプロ漫画家に提供して、アシスタントをする家弓に、数子と勉も否応なく巻き込まれていくというエピソードがあるのだが、そこで数子が目撃するのは、今まで自分に課してきた学業エレベータ経由で少数者に入るための努力・克己を凌駕する、大衆へメッセージを発信するという特権を持った漫画家の、「ヤバさ」である。二徹・三徹当たり前、着物は虚飾のためじゃなく、「寝たらしわになる」という女の虚栄心を使って眠らないために着るのだ。ヤバイ。学業エレベータでトップを取るのにも気が狂うような努力をしてきたつもりだったけど、この漫画家という人種はヤバ過ぎる。女としてとか、知性レベルであるとか、そういう所で比較する以前に、この人種とは関わってはいけない! 二徹でベタ塗りアシスタントを終えた数子が、漫画家を志望する家弓とは縁を切ろうと決意するシーンは名シーンである。何が名シーンかって、そう決意しながら、数子はそれまでになく満ち足りた表情をしていたから。
そういう感じで、少数者に入る実力がある学業エレベータのトップオブトップだけど本質的に大衆者の数子、大衆者だけど少数者とかそういうレベルじゃなくヤバイ漫画家を目指してる家弓、医大志望の二浪生で、少数者に入りたいんだけど数子と違ってその実力も才能もない勉とで雑居生活は続いていく。名作である。
------------------------
特筆すべきは、本質的に大衆者である数子は、叔父さんに認めて貰うために、自身の本質を曲げて学業エレベータを登り切るということしか、その当時は選択肢がなかった、もっと言うなら数子にはその選択肢しか見えなかったという悲劇です。結局叔父さんは大衆的な弱小演劇サークルで活動する女子大生と結婚してしまう所から物語が始まるので、実は、叔父さんのハートをゲットする条件としては、「少数者」入りする必要は最初からなかったということになります。
選択肢が今に比べてまだまだ少ない時代という背景を上手く使ったコメディ作品な訳ですが、もし現在の逆に選択肢がとまどってしまうほどに爆発的に増えた時代に数子が生きたなら、叔父さんのハートをゲットするために、どういう戦略を選択したのか? というのは、興味深いし、また形を変えて自分でも書いてみたい題材でもあります。
去年氷室冴子さんが亡くなってしまったので正統な続編を読む機会は永遠に失われてしまいましたが、主題自体は色々な最近のフィクションに受け継がれているとも思います。
つまる所、圧倒的な努力で能力値を上げきった人間が、大衆を前にした時、どういう選択を取るべきなのか。
結局の所、倉橋数子は、圧倒的な能力値を持ちながらも一番欲しいもの(叔父さん)は手に入らず、そしてどうしようもなく大衆を捨てきれず、さんざんな感じでぐだぐだと家弓と勉と雑居生活を続け続けた所に、この作品が時代を超えて読み継がれている名作たる所以があると思うのでした。

雑居時代〈1〉―Saeko’s early collection〈volume.7〉 (saeko’s early collection volume. 7)

雑居時代〈2〉―Saeko’s early collection〈volume.8〉 (saeko’s early collection volume. 8)
●あと山内直美さんの素晴らしい漫画版が花とゆめコミックスで3巻、白泉社文庫版で2巻出ていて、ブックオフなんかにわりと置いてあるのでそっちから入るといいかも。氷室先生の文章も凄いのでいつか原作小説も読んで欲しい作品ですが。